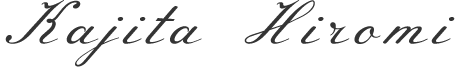昨日は<旅先で体調万全をキープする5つのポイント>
と題しまして5つのポイントを紹介しました。
読んでいらっしゃらない方はこちらから↓↓↓
【旅先で体調万全をキープする5つのポイント】
- 食事はお腹いっぱい食べない。
- 行った先で食べるであろう地元の物に対処できる<毒だし>を準備していく。
- 旅の期間はよく歩く、動く、ランニングをする。
- 気功をする。
- 珍しいもの、食べなれていないものは自分の身体と相談して食べる。
この5つでしたね。

今日は1と5について解説します。
まず1の<食事はお腹いっぱい食べない>について。
1日2回か3回、食事をする機会があると思います。
私もジョージさんも普段は1日2食が基本です。
でも旅行中は朝ご飯を家族みんなで食べることが多くなります。
そんな時に心がけるのは少食。食べ過ぎないことです。
常にお腹が軽い状態にしておくと、身体はとても楽ちんです。
目安としては食後にだるさや眠気に襲われない程度の食事量であり
「もうちょっと食べたいな」と思うところでやめておくのがポイント。
飽食の現代、不調のほとんどは食べ過ぎが原因です。
食べた後に動くのが億劫になるほど食べては観光も楽しめません。
食べる楽しみは<お腹いっぱい食べないこと>で本当の楽しみに変わります。
これはゆきにも伝えてあります。
といっても…子供に「食べ過ぎない」伝えても
なかなか難しいのが現状ですが
それは身をもって体験してもらっています。
だから失敗する時も、もちろんあるんです。
でもこれってすごく重要な体験で
「私はこれくらい食べたら、こんな風になるんだ。」
という自分自身の目安を知っていくために必要な過程。
こればかりは親がどんなに口をはさんでも
子供自身が本当の意味で体得するのは難しいと思います。
だから母はだまって見守るべし。
万が一の時は手当でお助けしています。
ちなみにゆきは食べ過ぎたら
鼻血が出たり、だるくなって、眠くなって、機嫌が悪くなる。
(超わかりやすい…笑)
そんな時は
「そこまで食べると食べ過ぎってことだね」
と一言添えています。
(最近は本人が1番わかっているので言わないようにしていますが…)
小さいころから、そうやって自分の身体と対話していると
最近では「これはもうやめておく」というように
自分の必要量を自分で判断できるようになってきました。
大人の場合は理性も働きますから…笑
食べ過ぎないことを心がけることで十分成果があると思います。

続いて5の「珍しいもの、食べなれていないものは自分の身体と相談して食べる。」について。
これも考え方は1と同じです。
普段食べなれていないものはいきなり大量に食べないこと。
私は普段の食事は菜食ベースですが、
今回の和歌山のようにお魚が美味しいところに行ったら
やっぱり味わってみたいと思います。
しかし、もともと火を通していない生のお魚をたべるとお腹が緩くなる
という自分の特性を理解しているので、
ジョージさんが頼んだお刺身を少しいただく程度にとどめます。
他にもその土地でしか食べられない野菜や料理、
その土地でしか食べられない和菓子(茶道をやっていますから気になります)も
やっぱり試してみたい。
<風土はFOOD>というくらい土地の暮らしは食事に反映されるものです。
その土地を知ろうと思ったら、食べ物を知ることってとても大切。
でも、いただく量は一口だっていいわけです。
無理して1人分食べる必要はありません。
1人分として出てくるものはお店が勝手に決めた量であって
私の適量ではないのです。
そういう意味では<自分の適量を知る>ことは
大人も子供もとても大切です。
だから1人分を注文して家族3人で分けることもよくあります。
ゆきと私は1口ずつ食べて、そのほかはジョージさんがいただくってことだってある。
みんな一緒の量でなくてもいいし、お店の基準に合わせなくてよいのです。
ちなみにですが私の場合は
「身体に合ってないよ~そろそろ控えて~」のサインは
肝の経絡にうずくような感覚が出てくる時。
これは気功をするようになって分かるようになった感覚です。
でもこの特別な能力ではなくて、
気功を地道に続ければ、ほぼ全員の方が分かるようになりますので
興味がある方はぜひ毎週開催の気功教室へ。↓↓↓
【5月東洋医学×気功教室】
ゆきの身体にあってないよのサインは、
食べ過ぎの時と同じ反応がでます。
経絡を使わないで目安を知る方法としては・・・
やっぱり食後のだるさや眠さがヒントになります。
食べた後でもすっきり動ける程度がちょうどいい量です。

さて、今日は1と5について紹介しました。
これは旅先だけでなく、普段の食生活でもいえること。
おいしい食事はついつい食べ過ぎてしまいますが
普段から自分の身体の適量を知っておくことは
楽しく過ごす上でとても役立ちます。
食後の身体の反応や感覚にぜひ耳を澄ませて
毎食毎食自分の身体と仲良くなっていきましょう。
耳を澄ませる…というとちょっと抽象的なのですが
「どうかな?」
「これくらいかな?」
「心地よいかな?」
という視点を持つと感覚に敏感になることができます。
初めから正解を当てに行くのではなく、
試して試して知っていくというスタンスだと
自分自身との対話を楽しんで続けていけますよ。
今からだって遅くないです。
きっとあなたの身体は、
あなた自身が身体の声に耳を澄ませてくれるのを待っています。
それでは今日も
人生最高の1日を☆彡